ピラティスマットとヨガマットの違いを厚さ・素材・クッション性・用途別で徹底比較。どちらを選ぶべきかわからない人向けに、両者の設計意図や使用感の違いをわかりやすく解説します。初心者でも安心して選べるよう、メリット・デメリットを整理して紹介します。
ピラティスマットとヨガマットの1番の違いは「厚さ」

ピラティスマットとヨガマットの最も顕著な違いは、その「厚さ」にあります。一般的に、ヨガマットは3〜6 mm程度の薄型が主流で、バランスポーズやグリップ性を重視した設計です。一方、ピラティスマットは6〜12 mm以上の厚手仕様が多く、特に10 mm以上のクッション性のあるものが推奨されています
ヨガのポーズでは立位や片脚バランスが多く、マットが厚すぎると沈み込んでしまいバランスが取りにくくなることがあります。そのため、薄手で床反力を得やすくグリップ性の高いヨガマットが適しています。一方、ピラティスでは仰向け・うつ伏せ・腹臥位など床に背骨や坐骨を接する動作が多く、厚さがないと肘や膝、腰などに床の硬さが直接伝わり、痛みや不快感を伴うことがあるため、厚手マットが求められます。
初心者や自宅で併用したい場合、6〜8 mm程度の中厚タイプも選択肢ですが、どちらかに特化して練習するなら、ピラティス主体なら10 mm以上、ヨガ主体なら3〜5 mmが推奨されます。これにより、快適性とパフォーマンスの両立が可能です。
素材(PVC/TPE/NBR/天然ゴム)の違いと特徴

ピラティスマットとヨガマットのもう一つの重要な違いは、「素材の種類」にあります。主に使用される素材は、PVC(ポリ塩化ビニル)、TPE(熱可塑性エラストマー)、NBR(ニトリルゴム)、天然ゴム(ナチュラルラバー)の4種類で、それぞれに特徴とメリット・デメリットがあります。
PVC(ポリ塩化ビニル)
PVCは最も普及している素材で、比較的安価で耐久性が高く、汗や汚れにも強い点が特徴です。ただし、やや硬めで環境負荷が高く、においが気になることもあります。ヨガマット・ピラティスマット両方に使われていますが、やや「人工的な質感」が気になる人も。
TPE(熱可塑性エラストマー)
TPEはエコ素材として人気が高く、PVCよりも軽量で柔らかく、適度なグリップ感とクッション性があります。水洗いも可能で衛生的。ピラティスマットでは、クッション性と軽さのバランスが求められるため、TPE製がよく選ばれます。環境にも優しい素材です。
NBR(ニトリルゴム)
NBR(ニトリルゴム)は、スポンジのようにもちもちと柔らかで弾力性に優れます。水にも強い性質なので、洗うことができるため、清潔に保ちやすいです。安価なところもメリットです。デメリットは、折りたたむとしわになりやすいことと、柔らかくてポーズによってはグラつく可能性があることです。ピラティスマットに採用されていることが多い素材です。
天然ゴム(ナチュラルラバー)
天然素材で作られたナチュラルラバーは、抜群のグリップ力と安定性を誇ります。特にヨガの立位ポーズでは滑りにくく安定するため、上級者に好まれる傾向があります。ただし、重さがある・価格が高い・ゴムアレルギーに注意が必要という点もあります。
ピラティスでは「快適さ」や「クッション性」が求められるためTPEやPVC、ヨガでは「滑りにくさ」や「安定性」が重視されるため天然ゴムが選ばれる傾向があります。素材選びは「どのエクササイズで何を重視するか」によって変わるため、自分の運動スタイルに合わせて選ぶのがベストです。
サイズと形状の違い(長さ・幅・携帯性)

ピラティスマットとヨガマットでは、サイズと形状にも明確な違いがあります。両者とも一見すると似ていますが、目的と使用姿勢の違いによって設計が大きく異なっているのです。
長さの違い
ヨガマットの一般的な長さは約170~180cm程度で、成人女性の身長に合わせて設計されています。ヨガは主に立位や片足バランスのポーズを中心に行うため、足がしっかり収まる長さがあれば十分です。
一方、ピラティスマットは180〜190cmと、やや長めに設計されています。これは仰向け・うつ伏せ・四つ這いなど、全身をマットに預ける姿勢が多いため、頭からかかとまでがしっかり収まるサイズ感が求められるからです。
幅の違い
幅に関しても、ヨガマットは60〜65cmが標準で、ポーズに必要なスペースをカバーしています。対して、ピラティスマットは65〜75cmとやや広め。体の横方向への動きが多いエクササイズに対応できるよう設計されています。
携帯性・収納性の違い
ヨガマットは軽量で折りたたみやすく、外出先やスタジオへの持ち運びに便利なように設計されています。一方、ピラティスマットは厚みとサイズがあるため、ややかさばりやすく、重さも増します。自宅トレーニング中心のユーザーに好まれやすい傾向です。
また、最近では折りたたみ式・軽量モデルなど、ピラティスマットでも携帯性に配慮された製品も増えてきています。選ぶ際は「練習場所」「収納スペース」「移動の頻度」などの生活環境を加味することが大切です。
このように、マットのサイズや形状の違いは、ピラティスとヨガそれぞれのエクササイズの特性に直結しています。
グリップ力と滑りにくさの比較

グリップ力(滑りにくさ)は、マット選びにおいて非常に重要なポイントの一つです。特にポーズ中に手足が滑るとフォームが崩れ、怪我や効果の低下につながるため、用途に応じた最適なグリップ性能を選ぶことが求められます。
ヨガマットのグリップ力
ヨガは、立位や片足でバランスを取るポーズ、ダウンドッグのような手足をしっかり固定するポーズが多いため、マットのグリップ性能が非常に重要です。
そのため、ヨガマットは表面に滑り止め加工(凹凸のテクスチャ)が施されていたり、吸汗性・速乾性のある素材(天然ゴム・PUなど)を使用しているものが多く見られます。特にホットヨガでは、汗をかいても滑りにくい加工が必須です。
ピラティスマットのグリップ力
ピラティスの場合、仰向けやうつ伏せなど、マットの上に体を預けるポジションが多いため、そこまで強いグリップは必要とされないのが一般的です。それよりも、肌への当たりが柔らかく、滑らかな触感であることが求められるため、PVCやTPE、NBT素材の中でも「やや滑るがクッション性に優れる」タイプが主流です。
ただし、体幹トレーニングや四つ這い・プランク系の動きが多い場合、滑りやすいマットだと手がずれて危険になることもあるため、ピラティス用でも適度なグリップは必要です。特にフロー系やアスリート向けのハードピラティスでは滑りにくさも考慮すべきでしょう。
グリップ力を選ぶ基準
- ヨガ重視:天然ゴム・PU・テクスチャ加工ありの薄型マット(3~6mm)
- ピラティス重視:TPEやNBR、PVC製で厚みとクッション性重視(8~12mm)
グリップ力が強すぎると体の移動がスムーズにいかず、逆に動きづらくなることもあるため、適度な滑りやすさと止まりやすさのバランスが重要です。購入前には実際に手を乗せて滑りやすさをチェックするのがおすすめです。
快適性と安全性:クッション性の重要性
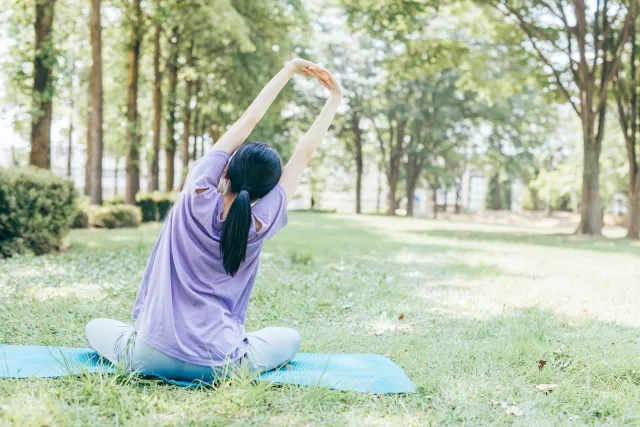
マット選びにおいて「クッション性」は、快適性と安全性の両面に大きく関わります。特にピラティスでは床と体の接触時間が長いため、適切なクッション性がなければ骨や関節に不必要な圧力がかかり、痛みやケガにつながるリスクがあります。
ピラティスでのクッション性の重要性
ピラティスでは、仰向けで背骨を床に沿って動かす「ロールダウン」や、「ハンドレッド」「レッグサークル」などのエクササイズで骨盤や尾骨を床に接する場面が多々あります。こうした動作の際にマットが薄すぎると、骨が直接床に当たり、痛みや違和感を感じやすくなります。
このため、ピラティスマットでは10mm以上の厚みが推奨されることが多く、特に初心者や体重が軽い女性、高齢者にとってはクッション性の高さが安全な運動の継続をサポートします。
ヨガではクッション性が高すぎると逆効果?
一方ヨガでは、クッション性が高すぎるとポーズのバランスが取りにくくなり、不安定になってしまいます。特に立位のポーズやアームバランス系の動作では、沈み込むマットだと安定感を欠くため、ヨガマットは3〜6mm程度の薄さが主流です。
ただし、膝立ちや座位のポーズが多い方には、6〜8mmのマットも選ばれることがあります。この場合は「沈み込みすぎず、なおかつ痛みを感じない」絶妙な厚さのマットを選ぶことがポイントです。
安全性にも関係する
クッション性が不足していると、関節への衝撃吸収が不十分になり、手首・膝・腰などへの負担が増大します。逆に柔らかすぎると、正しいフォームが保てず、トレーニングの質が低下する恐れも。自分の体のコンディション(筋力・柔軟性・体重)に合わせて、適度なクッション性のあるマットを選ぶことが、ケガ防止と快適な継続につながります。
このように、単なる厚い or 薄いだけでなく、使用目的や自分の体に合ったクッション性を選ぶことが、安全で効果的な運動を行う上で非常に重要です。
ピラティスマットとヨガマットを併用する場合の選び方と推奨厚み

ピラティスとヨガを両方行っている人にとって、「マットを分けるべきか、1枚で済ませるべきか?」というのは非常に多い悩みのひとつです。スペースやコストの都合から1枚で併用したいという声も多く、今回はその場合の最適な選び方と推奨厚みについて詳しく解説します。
両立したいなら「中厚タイプ」が基本
結論から言うと、6〜8mm前後の中厚タイプのマットが、ピラティスとヨガの両方をバランス良くこなせる厚みとして最もおすすめです。ヨガのバランスポーズにも対応できる安定性を保ちつつ、ピラティスでの仰向け動作にもある程度のクッション性を提供してくれます。
特にTPE素材や、やや密度の高いPVC素材を使用した中厚マットは、沈み込みが少なく、グリップ力と柔らかさのバランスがよいため、両者の特性をうまくカバーできます。
こんな人は2枚持ちがベスト
ただし、以下のような方には用途別に2種類のマットを持つことを推奨します。
- ヨガ中心で立位やアームバランスが多い
→ 3〜5mmの高グリップマット - ピラティス中心で仰向けや体幹トレーニングが多い
→ 10〜12mmの厚手マット - ホットヨガやパワーヨガなど大量の汗をかく
→ 滑りにくいPU・ゴム素材 - 体重が軽く骨への負担を感じやすい
→ クッション性重視のピラティスマット
併用時の注意点
ヨガの中でも「リラックスヨガ」「陰ヨガ」など、座位や寝ポーズが中心のスタイルなら、多少厚みのあるマットでも問題ないことが多く、むしろ快適性が増します。一方、パワーヨガやヴィンヤサ系では薄手でしっかりグリップするマットが望まれます。
一方ピラティスでは、あまりに薄いマットで骨盤や腰が痛むと継続が難しくなるため、併用したい場合でも最低6mm、できれば8mm程度のマットが理想です。
「1枚で済ませたい」という方には6〜8mmの中厚マット+TPE素材が無難な選択肢ですが、運動の目的やレベルに応じて、2枚持ちや使い分けを検討するのも長期的には効率的です。
購入前に確認したい重さや収納性のポイント

マット選びで見落としがちなのが、「重さ」や「収納性」といった使い勝手の部分です。特に自宅とスタジオを行き来する人や、限られた収納スペースでトレーニングをしている方にとって、持ち運びや保管のしやすさは重要な判断材料になります。
ピラティスマットの重さと収納性
ピラティスマットは厚みがあるぶん、重さが1.2〜2.5kg程度になることが一般的です。特に10mm以上の厚手マットや高密度素材のものは、しっかりとした重みがあります。サイズも長めで幅広のものが多いため、巻いてもかさばる傾向があり、持ち運びにはやや不便です。
ただし、自宅利用においては安定性があり、ずれにくいため重さはメリットにもなります。収納の際は、専用ケースやマジックテープでしっかりと固定するのがおすすめです。
ヨガマットの重さと収納性
一方、ヨガマットは0.8〜1.5kg程度が一般的で、薄手で軽く、丸めたときの直径も小さいため、持ち運びやすさに優れています。専用のストラップ付き商品や、ショルダーバッグに収まるコンパクトサイズのマットも多く展開されています。
スタジオ通いが多い人、公共交通機関での移動が多い人には、軽くて巻きやすいヨガマットが非常に便利です。さらに、折りたたみタイプのトラベルマットなども登場しており、旅行や出張先でも活用できます。
素材による重さの違い
- TPE素材:軽くて柔らかく、収納しやすい
- PVC素材:やや重く巻きづらいが耐久性あり
- NBR素材:軽量で持ち運びにもぴったり
- 天然ゴム:非常に重くかさばるが滑りにくさ最強(持ち運びには不向き)
収納性で後悔しないために
収納場所が限られている家庭では、「吊るして収納できるフック穴付き」や「コンパクトに巻ける」マットを選ぶと、日常的に出し入れしやすく、継続につながります。また、使用後の汗や汚れを考慮し、お手入れのしやすさ(水洗いOK・速乾素材)もポイントです。
重さや収納性は、日々の使い勝手を左右する重要な要素。高機能なマットでも、使いづらければ継続できません。あなたのライフスタイルに合った持ちやすさや片付けやすさを意識して選びましょう。
品質・ブランドごとのおすすめ比較

マットの品質やブランドは、トレーニングのモチベーションや効果にも大きく影響します。安価なマットを使って滑る、すぐにへたる、臭いが気になるといったトラブルがあると、継続が難しくなってしまうことも少なくありません。ここでは、信頼性が高く、実際に評価されているピラティス・ヨガ向けマットのおすすめブランドとその特徴を紹介します。
おすすめのマットブランド
- GronG(グロング)
→ コストパフォーマンスが高く、厚手タイプ(10mm)でも2,000円台~とリーズナブル。自宅用として人気。表面の肌触りも良く、初心者にも安心。 - La-VIE(ラヴィ)
→ スポーツ用品量販店でも取り扱いがあり、品質と価格のバランスが良い。シンプルなデザインで飽きがこない。抗菌加工済モデルなども展開。 - Manduka(マンドゥカ)
→ プロヨガ講師の多くが愛用するプレミアムブランド。天然ゴムやPU素材を使用したグリップ力抜群の高品質マット。eKOシリーズやPROシリーズが特に有名。 - Liforme(ライフォーム)
→ 滑りにくさとデザイン性を両立。ポーズの位置ガイドラインが印刷されており、初心者でも正しいフォームを意識しやすい。ホットヨガにも対応。 - ヨガワークス(YogaWorks)
→ 日本国内でも広く展開している信頼ブランド。軽量モデルやトラベル向けモデルもあり、持ち運びしやすく、価格帯も幅広い。
ブランド選びのポイント
- どこで使うか?(自宅 or スタジオ)
- 予算はいくらか?(2,000円台〜20,000円超まで幅広い)
- 滑り止め・クッション性のバランス
- 口コミ・レビューの確認
価格だけで選ぶと、数回の使用で劣化したり、滑って危険だったりと、結局買い直すことになりがちです。信頼できるブランドを選ぶことで、トレーニングの質も大きく向上します。自分の運動スタイルやこだわりに合わせて、最適な一枚を選びましょう。
よくある誤解と質問への回答(FAQ形式)

最後に、「ピラティスマットとヨガマットの違い」についてよくある疑問や誤解をFAQ形式でまとめて解説します。特に初心者やこれから購入を検討している方に向けて、安心して選べるようにわかりやすく整理しました。
このようなよくある質問を把握しておくことで、マット選びに失敗するリスクを減らすことができます。使い続けるうちに自分に合った理想のマットが見えてくるはずですので、まずは自分の運動スタイルに合った「最初の1枚」を選びましょう。
記事全体のまとめ「【徹底比較】ピラティスマットとヨガマットの違いをまるごと解説」

ピラティスマットとヨガマットは、見た目こそ似ていても、厚さ・素材・サイズ・用途・グリップ力・快適性など、あらゆる点で明確な違いがあります。それぞれの運動における体の使い方や目的が異なるため、マット選びの正解も変わってくるのです。
特にピラティスでは、10mm以上の厚みと高いクッション性が体の保護と正しいフォーム維持に不可欠。一方、ヨガでは3〜6mm程度の適度な薄さとグリップ性が、バランスポーズの安定性を高める鍵になります。
また、両者を併用したい場合は6〜8mm程度の中厚マットや、軽量なTPE素材の選択が有効です。ただし、本格的にどちらかを追求したい場合は、それぞれ専用マットを用意する方が快適性・安全性ともに高まります。
素材やブランド、収納性、耐久性などの細かい要素も踏まえたうえで、「自分の身体・目的・生活スタイルに合ったマット」を選ぶことが何より大切です。
間違ったマット選びは、フォームの崩れや痛み・ケガの原因となり、継続を妨げる最大の要因にもなり得ます。この記事を通じて、正しい知識をもとに、自信を持って自分に最適な1枚を選んでいただければ幸いです。